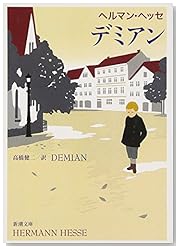神の名はアプラクサス 『デミアン』
2017/09/16
20世紀初頭のドイツの様子を知りたくて、手近にあった『デミアン/ヘルマン・ヘッセ(高橋健二訳)/新潮文庫』を読んでみた。これから書こうとしている小説の舞台を1900年頃のドイツ(もしくはそれに似た国)にしたいので、その参考文献だ。 暖炉、ほしたくだもの、焼きグリ、馬、時計の音、などいくつかの情報を得ることができた。
それはそれで有意義だったのだが、変な読み方をしたせいか、本来の『デミアン』をまったく理解できなかった。いや、真面目に読んでも私の頭では解読不能だっただろう。
物語は主人公シンクレールが幼年期から青年期に至るまでの魂の冒険を語っている。シンクレールは、物語全般に登場するデミアンの他、ピストーリウス、エヴァ夫人らとの対話を通して、キリスト教の矛盾、善と悪、個人の運命との対峙などについて思索を深めていくのだが、その思考についていくのは困難だった。
しかしシンクレールはいったい何物なのか。夢を見、悩み、堕落し、復活する。周囲を嘲笑し、自分の中に入り込む。そんな主人公の姿に対し憧れや共感を感じることはなかった。
ヘッセは「しるしを持つ人」で私は「しるしを持たない人」なのだと割り切って、考えることを放棄した。恥ずかしいが、解らないものはわからないと言うしかない。